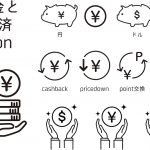ユニセフの歴史を振り返る
ユニセフは活動開始当初、国際連合児童緊急基金との名称で、第二次大戦後の緊急援助を必要とする子供たちに食料や医薬品などの供給を行なっていました。
日本も敗戦国として戦後の1949年から1964年にかけて主に脱脂粉乳や医薬品や原綿などの援助を受けていた経緯を持っています。
戦後の緊急援助が行き渡るようになり、各国の子供たちの栄養状態も回復傾向が顕著になり活動範囲が広がりをみせた1953年に、現代のユニセフの名称を有することになった訳です。
開発途上国や内戦や戦争などで被害をこむっている子供の保護や支援を活動の中心にすえているほか、子供の権利条約の普及活動も展開しているのです。
発足当初は物質の援助を中心にしていましたが、現在ではそれに止まらず、子供の自立なくしては根本的な貧困問題の解決に繋がらないとの問題意識のもと、親に対する栄養知識の普及なども積極的に行なっています。
それでは現在のユニセフは具体的にどのような取り組みを行なっているのでしょうか。
世界に目を移すと内戦や国際紛争は地域によっては深刻化を見せています。
シリアやイエメンの内戦や今後などの中央アフリカなどに典型的に見られるように援助を必要とする子供たちの数は膨大な数に上る訳です。
このような困難に直面しているものの、5歳未満の子供の死亡者数は着実に減少を見せています。
5歳未満の子供の死亡者数は着実に減少している
1990年には全世界で1260万人に上った5歳未満の死亡者数は、2016年には560万人にまで減少しているのです。
さらに栄養不良の子供も1990年以降確実に減少をしており、全世界レベルで見ると累計で26億人が新たに水源を確保できるようになりました。
公衆衛生の発達している先進国では感染症のリスクはさほど高くありませんが、途上国や貧困国では感染症の罹患率は依然高い水準にあり、中央政府が弱い、もしくは破綻している国ではコレラなどの感染症を猛威を奮っています。
水資源に乏しく戦乱などに明け暮れる国々では、しばしばコレラが流行を見せており、コレラ感染予防が喫緊の課題と認識されているのです。
そこで「コレラを管理する国債管理委員会」(GTFCC)が設置され、2030年までにコレラによる死亡者数を9割削減させることを目指した戦略を発表しています。
ところで現在のコレラの現況を確認しておきますと、感染者数は年間世界全体で290万人にのぼり、そのうち95000人が死亡していると盛られているのです。
日本ユニセフ協会より引用
汚染された水を媒介にして地域社会で感染者を広げるため、地域のコミュニティーを保持する上でも、コレラ対策の重要性は明白です。
コレラは年間流行する地域(ホットスポット)がある程度予測することが可能とされており、事前に対策をとることで感染拡大を防止し、発症をコントロールすることが出来る特長をもっているのです。
コレラの感染地域では基本的な水や衛生設備を整備することと経口投与ワクチンの導入によって、感染予防を図ることが叶います。
そこでユニセフでは感染地域などの水関連のインフラ整備や経口これらワクチンの普及の為の援助などに取り組んでいるのです。
水と衛生環境の整備が緊急の課題
このように感染症予防と栄養状態の改善の上では水と衛生環境の整備が緊急の課題です。
そこでユニセフでは、紛争地や災害地などの人道的危機に直面している2880万人の人々を対象に水や衛生関連の援助に取り組んでいます。
とりわけ水確保が生活の基本手インフラに位置することから、開発支援プログラムを通じて1000万人を越える人々が水へのアクセスが確保されるに至りました。
ところでアフリカ諸国の平均寿命を大きく引き下げている要因の一つにエイズ(HIV感染による免疫不全症)が挙げられています。
先進国では抗レトロウイルス薬の多罪併用療法が一般的となって、仮にHIVに感染してもエイズへの発症が食い止めることが可能になり、平均寿命を全うするHIV感染者も珍しくありません。
これに引き換えアフリカ諸国、とりわけサハラ以南の諸国ではエイズウイルス感染が猛威を奮っており、感染者数も膨大な数にのぼっています。
しかも、高い効果を見込める抗レトロウイルス薬は、アフリカ圏の国々の財政で賄えるほど安い薬価ではありません。
その結果アフリカ諸国では依然として、HIV感染後エイズを発症し死亡するのが後を絶たないのです。
しかも母子感染も深刻なものがあり、母親から子供へと感染が広がる事態には深刻なものがあります。
そこでユニセフではHIV陽性の母親に対して、妊婦の70%と子供の49%に抗レトロウイルス薬が投与出来るように支援活動を行なっているのです。
また抗レトロウイルス薬の供給支援にも本格的に取り組んでおり、2016年には1820万人の患者が抗レトロウイルス薬を服用出来るようになりました。
この数は2010年に比較しても倍以上に増加を見せています。
長年の取り組みの結果、アルメニア・ベラルーシ、タイではHIVの母子感染0に成功したとされているほどです。
最終更新日 2025年7月31日 by urisysym